ニュース
2026.01.08
労災補償保険法の改正 労災保険も男女による補償金受取の格差を解消する方向です

厚生労働省の労働政策審議会は、労災保険制度の見直しについて、遺族補償年金の支給要件の男女差解消などを盛り込んだ報告書案を了承した。
厚労省は今後、通常国会に改正労災保険法案を提出する予定。
現行制度では、年金を受け取る妻には年齢制限がない一方、夫の場合は55歳以上か一定の障害がなければ受取れない。
報告書案では「夫にのみ課せられた支給要件を撤廃することが適当」とした。
厚生年金保険法の改正でも、同様に男女間の格差および年齢による格差を解消しようという方向で、これと同じ方針です。
思い返せば社労士試験受験生時代に、「男性は55歳以上でなければ受け取れない」とか、試験の引っかけどころだったことを思い出しました。考えてみれば、こんなのは、ただの男女格差が理由だったのだ、と今更ながら理解しました。一所懸命暗記したのに・・・。
2025.11.19
2026年4月から在職老齢年金の支給停止調整額が62万円に引き上げられます
年金を受給しながら働く高齢者の賃金と老齢厚生年金の合計額が基準を超えた場合、老齢厚生年金が減額されます。
この基準が現在の月51万円から2026年4月に62万円に引き上げられます。

年金を受給しながら働く高齢者が、保険料負担に応じた本来の年金を受給しやすくなり、年金の減額を意識せず、より多く働けるようになります。
新たに約20万人が年金を「全額」受給できるようになると試算しています。
これにより、一部の業界で指摘される高齢者の働き控えを緩和し、人手不足の解消につなげようとの目的もあります。
しかしながら・・・この見直しにより、厚生年金全体の将来の給付水準を下げる影響があるが、今回の制度改正全体では給付水準は向上するという「ただし書き」があります。
本当に、これで良いのか???
2025.10.01
遺族厚生年金が「5年」で打ち切られる?!
2028年に厚生年金保険法が改正され「遺族厚生年金」の受給期間が5年の有期給付に変更になるなんて大変なこと!そんな驚きの声が上がっています。実際のところ、どうなんでしょうか?
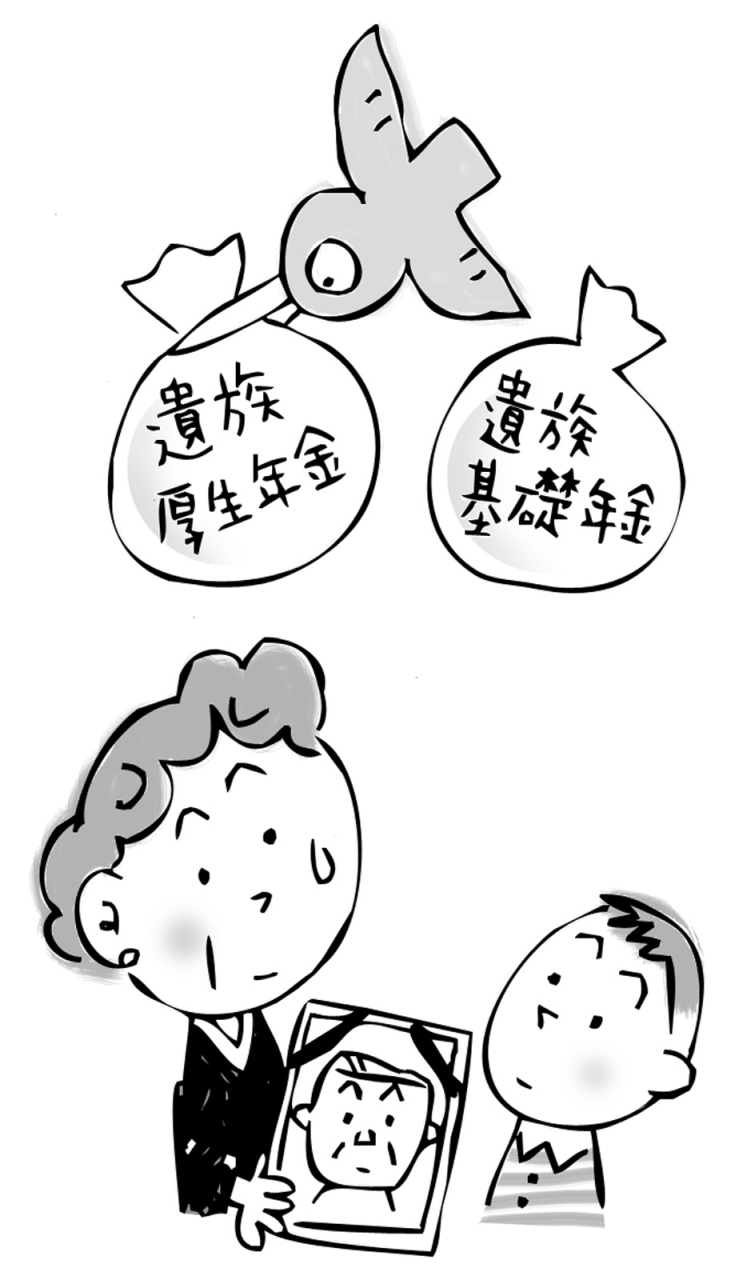
2028年4月施行予定の厚生年金保険法で、遺族厚生年金の受給期間が原則5年の有期給付に変更されます。どうして5年間しか受給できないの?という驚きの声がたくさん上がっています。法律の改悪に他ならない!という批判です。
現在の制度では「女性」の場合、配偶者(夫)との死別が、自身が「30歳未満」で「18歳年度末の子」がいない場合は「5年間」の有期給付
自身が「30歳以上」の場合は、無期給付です
もともと、30歳を境目にして、大きく給付内容が変わってしまうことが不合理であったため、この「30歳」という境目を失くし、一律5年にするということが大きな理由のひとつとしてあります。
18歳未満の子供がいる場合は、現行制度と同じ、という救済があることは、あまり多く語られず、5年で打ち切りという部分が強調されているように思えます。
確かに「30歳」以上で夫と死別してしまった女性にとっては、良い改正ではないとは言えます。
大切なことは・・・①すでに遺族厚生年金を受給している方②60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方③2028年度に40歳以上になる女性は、見直しの影響がないことです。
また収入が十分でない方は、5年有期給付の終了後も遺族厚生年金を受給することができる場合があります。
さらに、今回の改正で男女平等の観点から「男性」も受給することができるようになります(条件あり)。
他にも色々と制度上の救済はあります。全ての人が喜ぶ改正はなかなか難しい。一部分だけをとらえて批判してしまうことは慎みたいものです。
2025.09.07
2025年 最低賃金について答申状況が発表され大阪は1,177円に!
令和7年9月5日、労働基準局賃金課より地域別最低賃金の答申状況が発表されました。過去最高の上げ幅です!
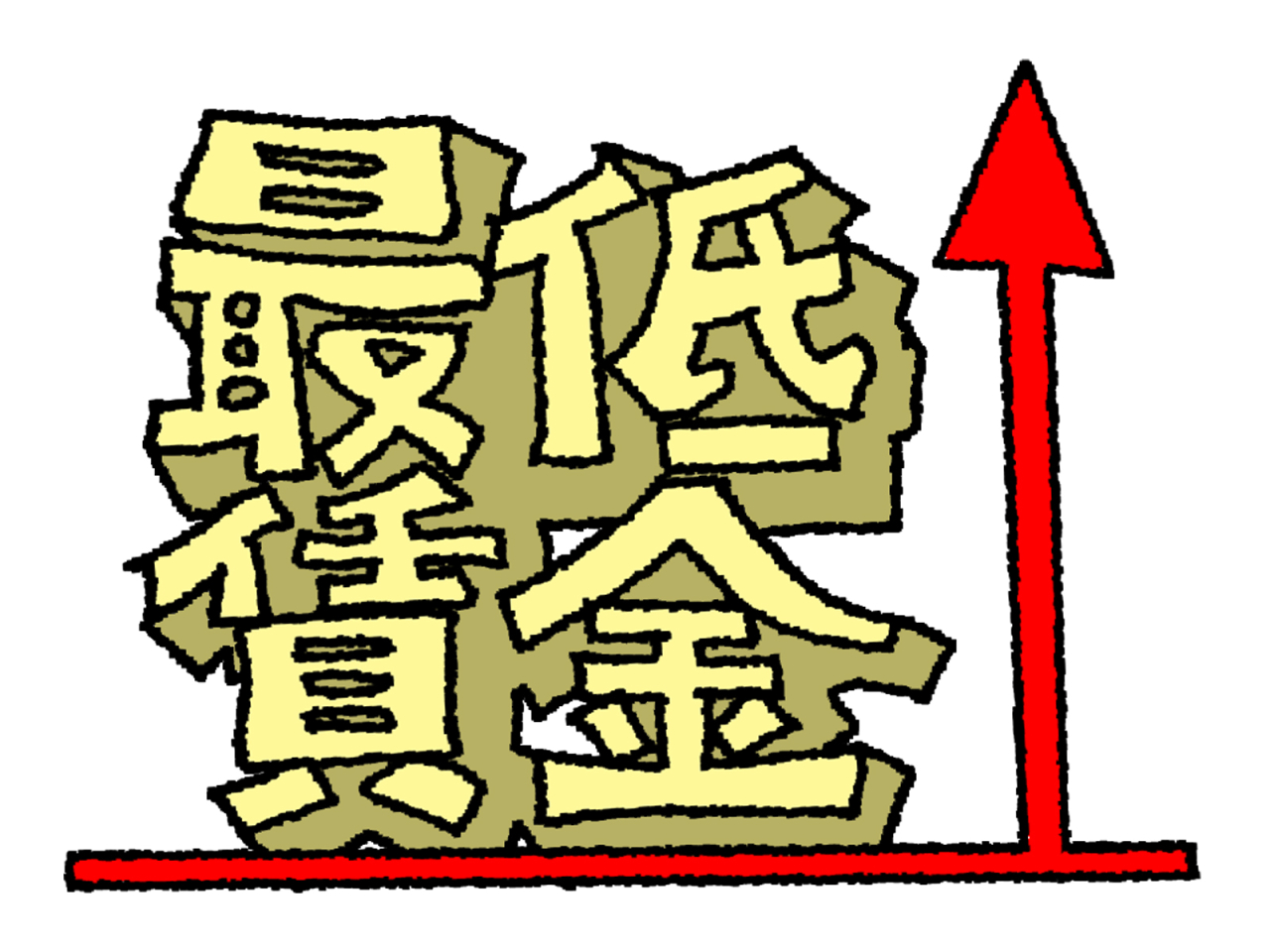
全国加重平均額は1,121円で、平均額66円の引き上げになり、昭和53年に目安制度が始まって以降で最高額
【大阪】 1,177円(前年比63円増額) 発効予定日10月16日
【京都】 1,122円(前年比64円増額) 発効予定日11月21日
【兵庫】 1,116円(前年比64円増額) 発効予定日10月4日
東京は1,226円で、引き上げ幅は63円
来年度もこれと同等か、これ以上に引き上る可能性があり、ここまで引き上ると時給契約のパートさんだけでなく、月給制の従業員に対する給与も時間換算して最低賃金を下回っていないか、近年中に下回る可能性がないか確認しておくことをお勧めします。
2025.07.16
労働者数50人未満の事業所にもストレスチェックの実施が義務化されます
職場のメンタルヘルス対策の推進を図るため、ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施することを義務とすることが決定しました。
ただし、施行まで十分な準備期間を確保するため、実施は3年後くらいになると思われます。
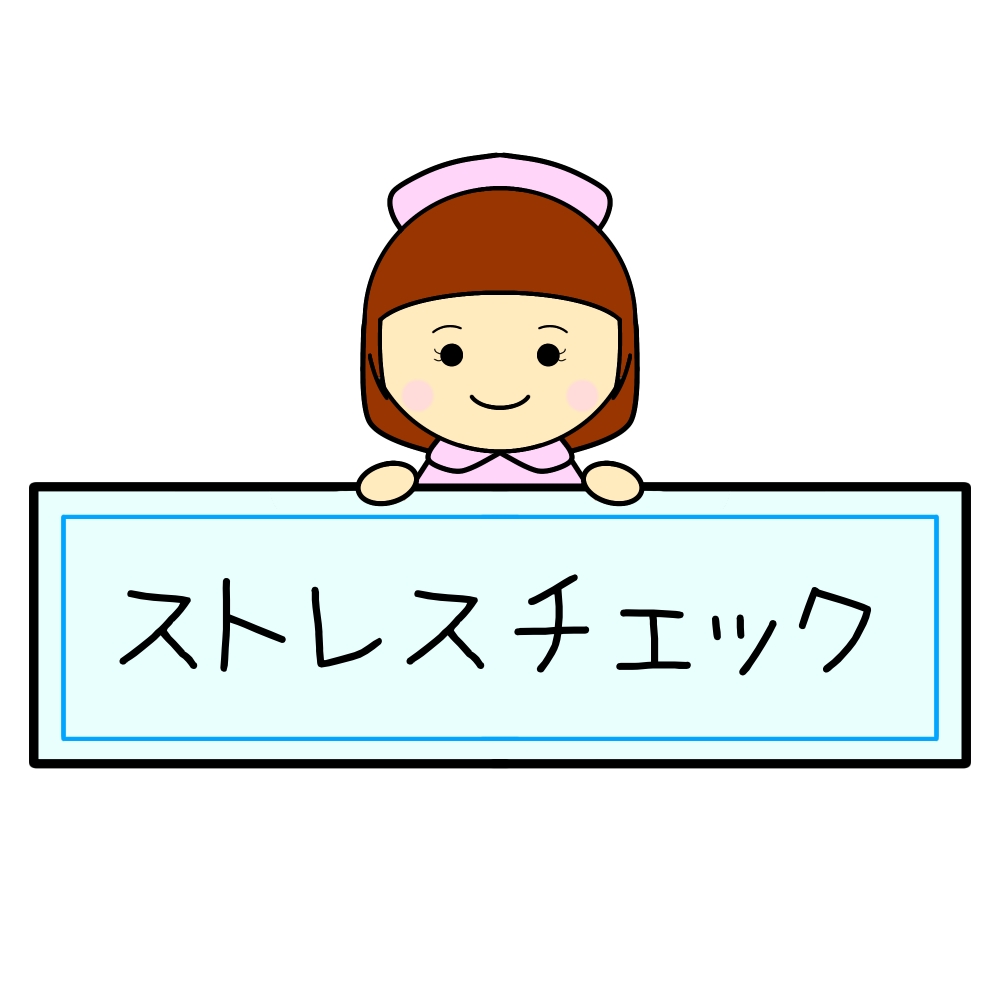
50人未満の小さな事業場でのストレスチェック義務化には、社会全体としてメンタル不調の防止を推し進めたいという思惑があります。
一方で、事業場側へのデメリットもあります。
現行のストレスチェック制度は50人以上の事業場で実施されることを想定しており、「産業医」の選任義務がなく、健康管理体制が整っていない小規模事業場がそれと同じように実施するには困難があります。
そこで国においても小規模事業者が円滑に制度改正に対応できるよう、50人未満の事業場に即したストレスチェックの実施体制・実施手法についてのマニュアルの作成や、医師による高ストレス者への面接指導の受け皿となる「地域産業保健センター(地さんぽ)」の体制拡充などの支援を進める予定です。
なお、義務化は3年後くらいになると思われます。
- 1 / 14
- »